AACとは?評価・導入・臨床での使い方と再評価のポイント【言語聴覚士(ST)向けガイド】
Miwa ありのままライフ
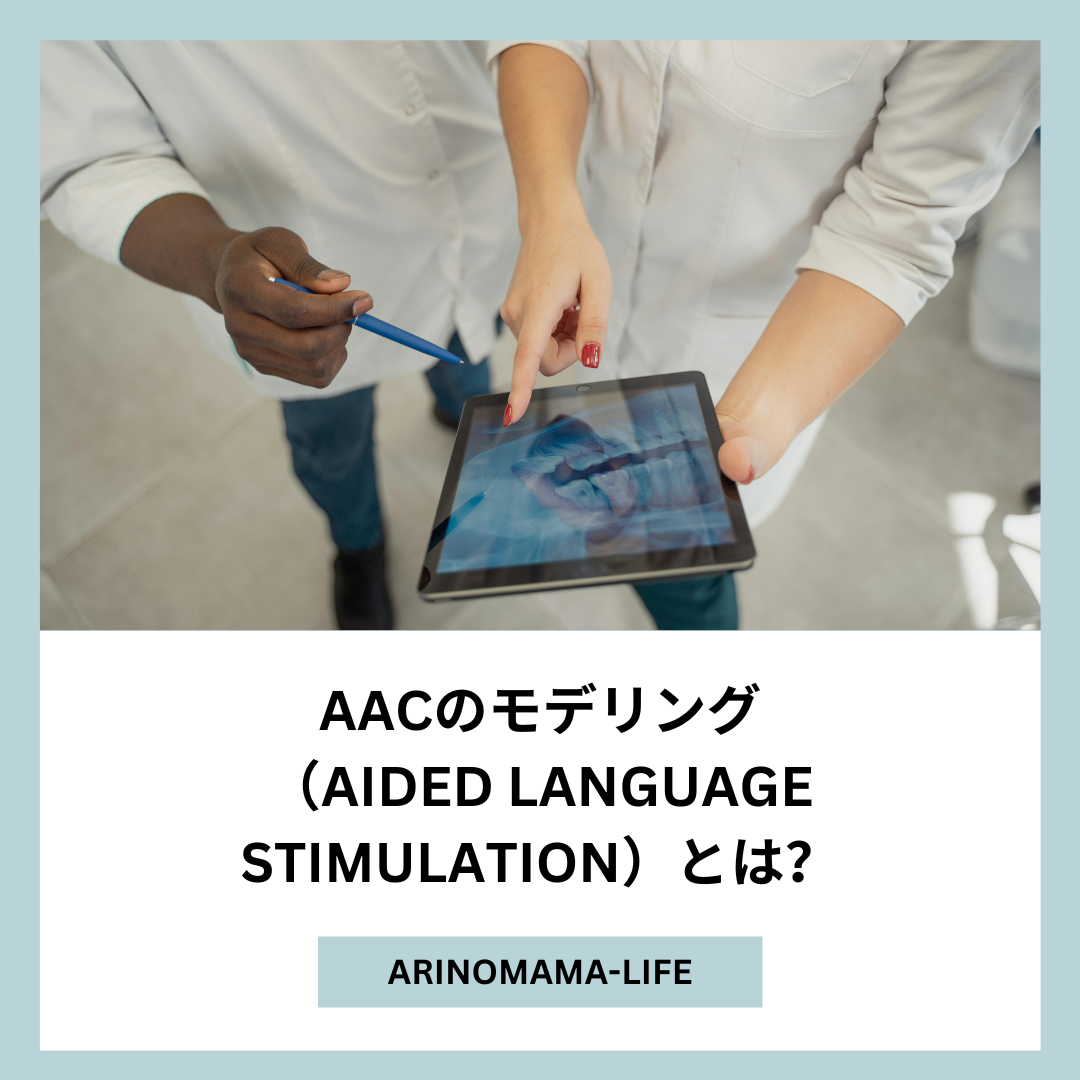
モデリング(Aided Language Stimulation / Aided Language Input)とは、AAC(補助代替コミュニケーション)ユーザーに対し、パートナーが話しかけながら同時にAACツールを使って語彙を示すインプット支援の方法です。
言葉と同様に、AACによるコミュニケーションも「聞く(見る)→まねる→使う」のプロセスが必要です。モデリングは、その「見せる(モデル化する)」部分に当たります。
したがって、AACシステムも“ことば”としてモデル化されなければ、子どもがそれを使って自発的に表現するのは困難です。
| 原則 | 説明 |
|---|---|
| 音声+シンボルで話す | 話しかけながら、AAC上でキーワードを示す(すべて入力しなくてよい) |
| 完全な文にこだわらない | 重要語彙のみでもOK(例:「きょう」「がっこう」「たのしかった」など) |
| 子どもが使えなくても先に見せる | 使用の前に、まず「見せて慣れさせる」ことが大事 |
| エラー訂正をしない | 子どもが間違えても修正しすぎない。自然な流れの中で再モデリングする |
| 日常の流れに取り入れる | 学校、家、外出先など、実生活の中で何度も繰り返す |
| 場面 | 発話例 | AAC操作例 (CboardやTwinkleなど) |
|---|---|---|
| 朝の会 | 「きょうは くもり です」 | [今日] → [天気] → [くもり] |
| 遊び | 「ボール やってみよう」 | [ボール] → [やる] |
| おやつ | 「もっと ください」 | [もっと] → [たべる]/[ちょうだい] |
📌 ポイント:完璧にすべて入力しなくても、「意味ある語彙」を強調するだけでも効果的
複数の研究で以下のような効果が報告されています。
✅ モデリングは「発語を奪う」のではなく、「言語発達を支える手段」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| モデリングとは | AACでの語彙を、支援者が見せながら使うこと |
| 目的 | AACを“ことば”として学ぶ環境をつくる |
| STの役割 | 家族や支援者に方法を伝え、継続的な実践を促す |
| 成果 | 表出の増加・文構成の改善・発語の促進効果あり |
▶︎【AACってなに?】話せなくても伝えられる!補助代替コミュニケーションの基本
▶︎【初心者向け】Twinkle AACのシンボル機能とは?絵カードで子どもの「伝えたい」を引き出す方法
▶︎【話せなくても伝えられる】ホーキング博士から学ぶAACの力|発達障害のある子どもと家族のために