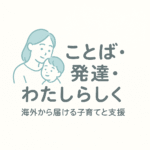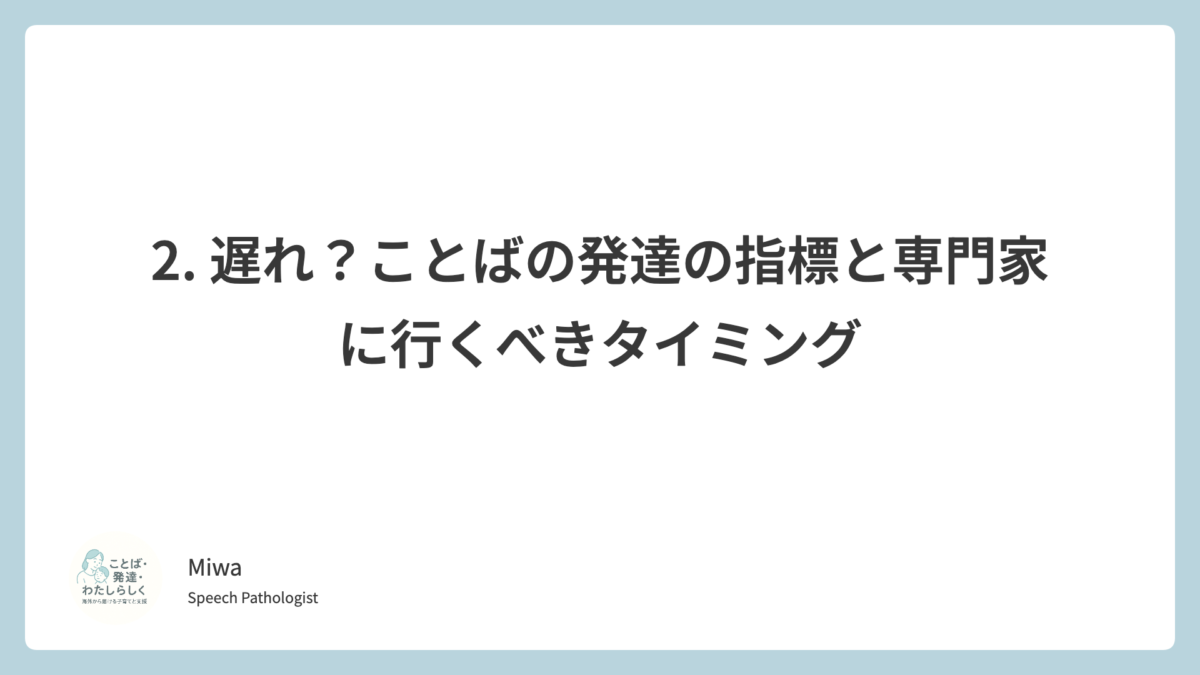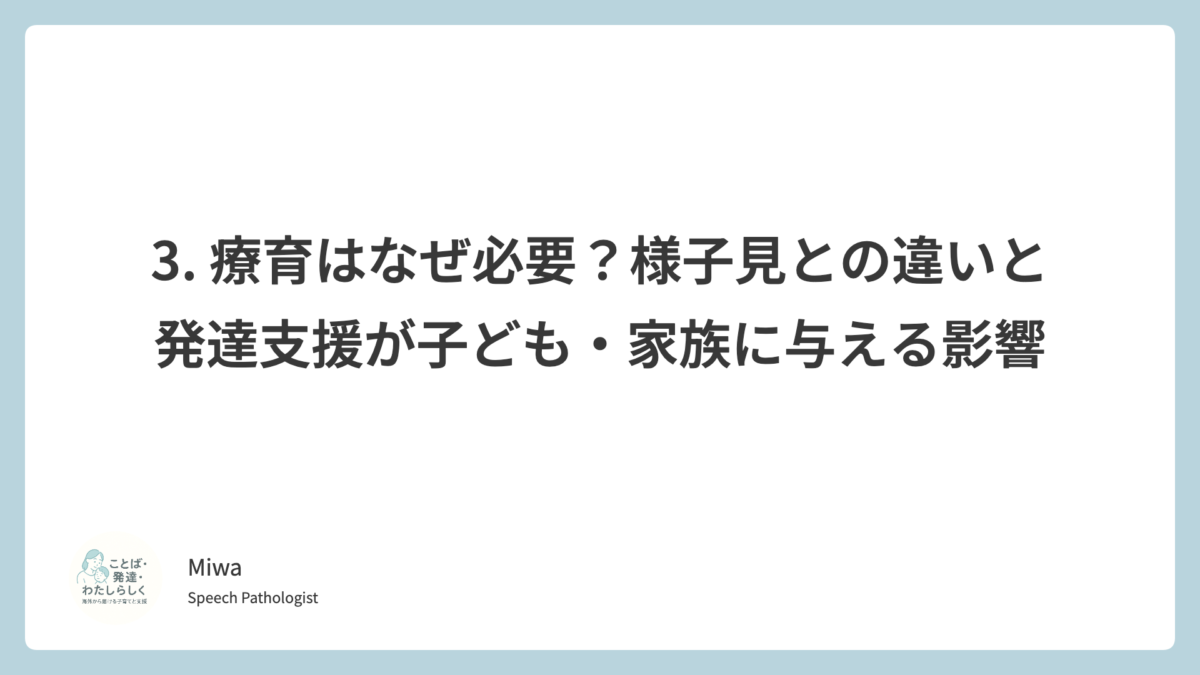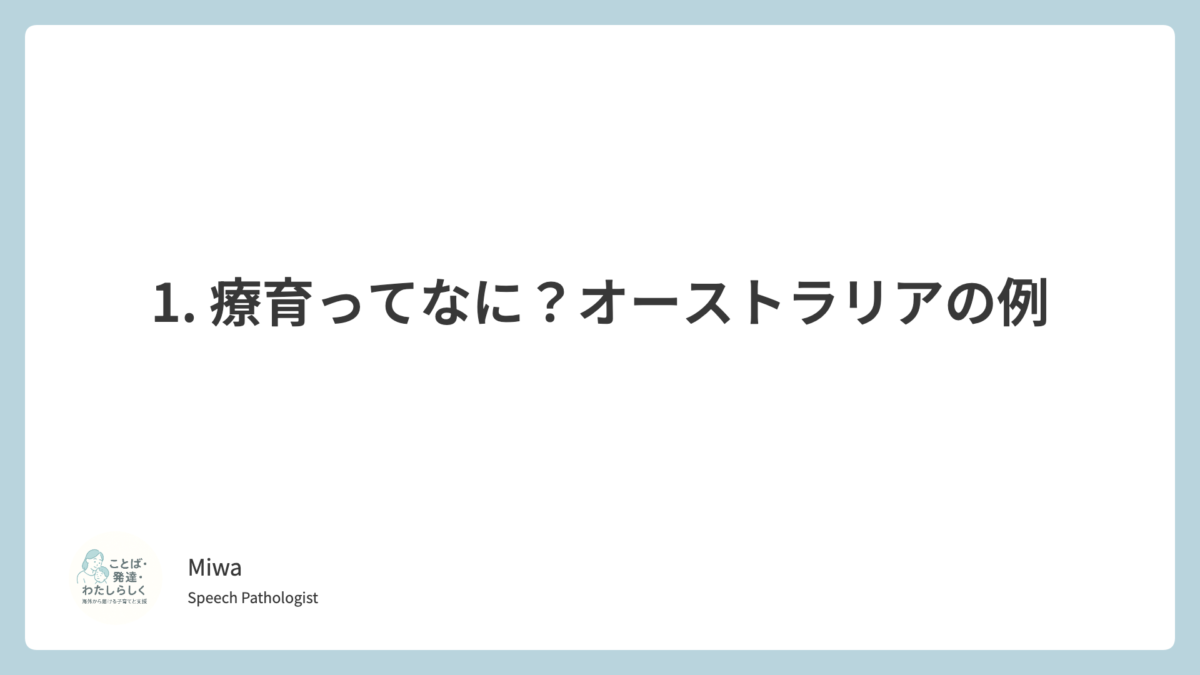4. 海外と日本の療育の違い(制度・文化・考え方)
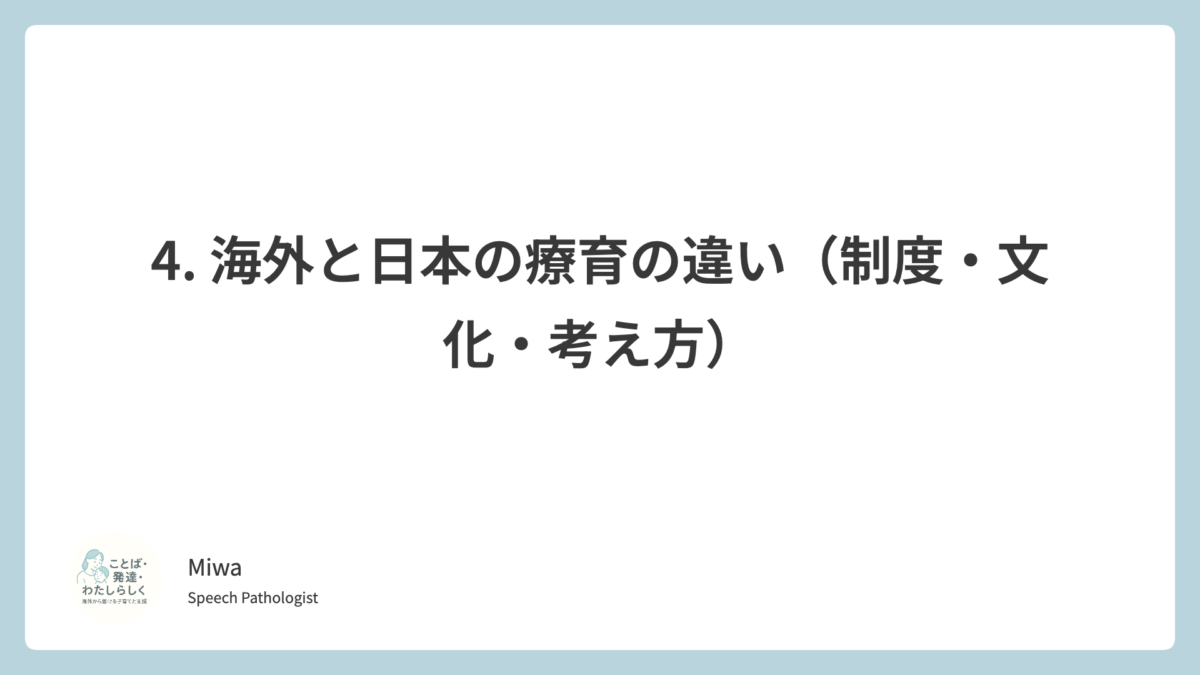
海外と日本の療育の違い(制度・文化・考え方)
はじめに
「海外の療育って日本とどう違うの?」「NDISやMedicareってどうやって利用できるの?」
オーストラリアで子育てをしている日本人家庭から、よくこんな声を聞きます。
実際にスピーチパソロジストとして働いている立場から、オーストラリアと日本の療育の違いをまとめました。
海外で暮らすご家庭が安心して子どものサポートを受けられるように、制度・文化・考え方のポイントを整理していきます。
オーストラリアの療育制度
NDIS(National Disability Insurance Scheme)
オーストラリア全土で使える全国統一の障害支援制度です。
対象は0歳から64歳までと幅広く、発達障害や言語の遅れ、自閉症スペクトラム、ダウン症など、日常生活にサポートが必要とされる子どもたちが利用できます。
申請には専門家のレポートが欠かせません。診断がなくても「継続的な支援が必要」と判断されれば対象になる可能性があります。
利用が決まると「プランナー」と相談して、スピーチセラピーや作業療法、心理支援などをどう組み合わせるかを決めます。
Medicare(メディケア)のケアプラン
GP(かかりつけ医)が作成するケアプランを利用すると、年間5回までスピーチセラピーや作業療法などのセッションが補助対象になります。
NDISに比べると範囲は限られますが、ハードルが低く「ことばが遅いかも?」と気づいたときに利用しやすい制度です。
学校でのサポート
オーストラリアの学校には「Learning Support」と呼ばれる仕組みがあります。
読み書きや言語の遅れに対応するため、教育支援員(Integration Aide)が入ったり、必要に応じてセラピストと学校が連携することもあります。
学校ごとに支援体制の手厚さは違うため、就学を控えた時期には「この学校でどんな支援が受けられるか」を事前に確認しておくことが大切です。
日本の療育制度との違い
日本では、自治体ごとに制度が分かれています。未就学児は児童発達支援、小学生以降は放課後等デイサービスが中心です。利用には「受給者証」が必要で、自己負担は原則1割です。
また、学校での支援は「通級指導教室」や「特別支援学級」が中心です。制度は整っていますが、オーストラリアのように全国統一ではなく、地域差があるのが現状です。
文化的な違いとして、日本は「先生に任せる」傾向が強く、家庭では日本語を重視する姿勢が一般的です。
一方オーストラリアでは「親もチームの一員」として療育に参加するのが当たり前で、家庭で話す言語(日本語)も大切にしてよいとされています。
海外に住む日本人家庭が知っておくと安心なポイント
- 家庭の日本語は大切にしてよい
英語環境でも、家庭の安心できる言語があることで、子どもは安心してことばを育てていきます。 - まずはGPに相談する
ことばの遅れや発達の不安を感じたら、GPに相談しケアプランを作成してもらうのが第一歩です。 - 必要ならNDISを検討する
専門家のレポートを集めて申請すれば、長期的な支援につながります。 - 学校選びも重要
インクルーシブ教育に力を入れているかどうかで、受けられるサポートに違いがあります。見学の際は「Learning Support」について質問してみるのがおすすめです。
まとめ
オーストラリアの療育は、NDISやMedicare、学校での支援が組み合わさっており、早期から多職種で関わることができます。
日本の制度も支援はありますが、自治体による違いや「親の関わり方」の文化がオーストラリアとは異なります。
海外に住む日本人家庭にとって大切なのは、家庭言語を守りながら安心して子育てできるように、制度を上手に活用することです。
療育は「ことば・発達・特性」に寄り添い、その子が自分らしく成長していくためのサポート。制度の違いを知ることは、不安を減らし、安心した子育てにつながります。