2. 遅れ?ことばの発達の指標と専門家に行くべきタイミング
Miwa ありのままライフ
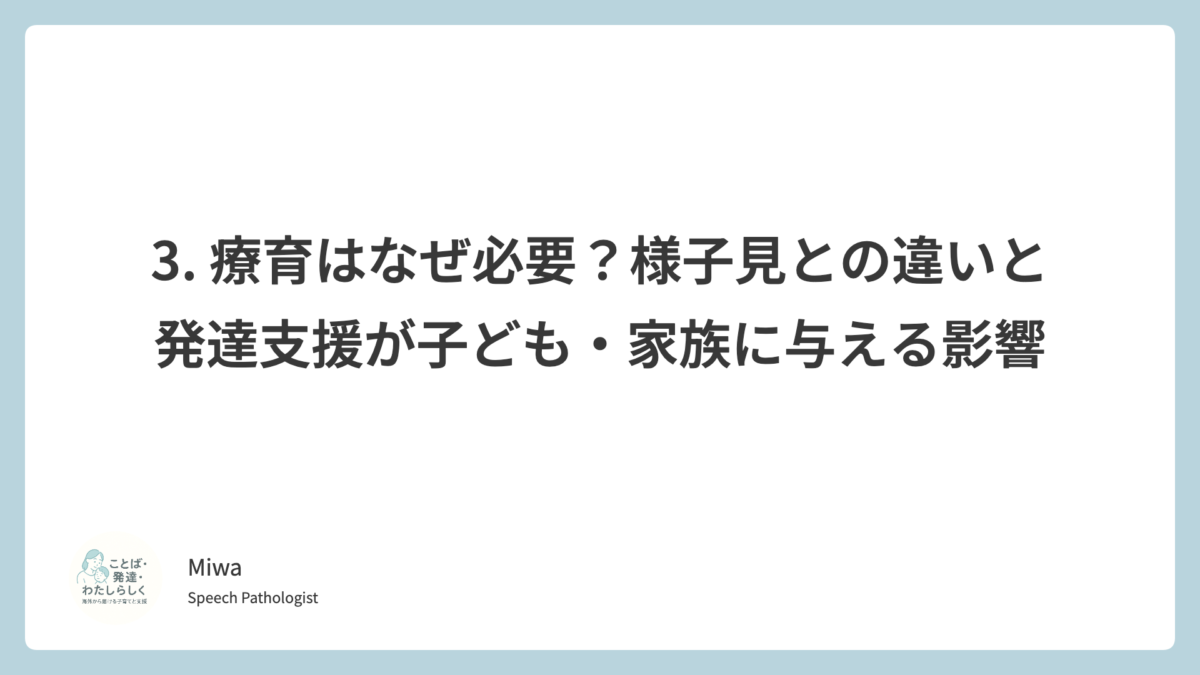
ことば・遊び・社会性の発達を土台から支える「発達支援」。早めに始めるほど、日常の小さな成功体験が積み重なります。
発達は「待てば伸びる」だけではなく、環境と経験の質に大きく影響されます。療育は、子どもが得意を活かしながら苦手を補うための“練習の場+やり取りの調整”です。
ごはん・お風呂・おでかけで、短く・繰り返し・視覚手がかりを使った声かけを定着。「もっと/おしまい」など実用語が増える。
見立て・ごっこ・ルール遊びで、順番・交渉・感情のやり取りが育つ。友だちとの関係づくりの土台に。
指示の受け取りやすさ・発表の準備・支援ツールの活用で、集団場面でも「できた!」が増える。
伝わらない→避ける→経験が減る…の連鎖を断ち、自尊感情・挑戦意欲を守る。
医療的に「経過観察」が適切な場合もあります。ただし日常で使えるコミュニケーション戦略は副作用がなく、今日から始められる支援です。
※本記事は一般的な情報です。医療的判断が必要な場合は医師にご相談ください。